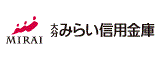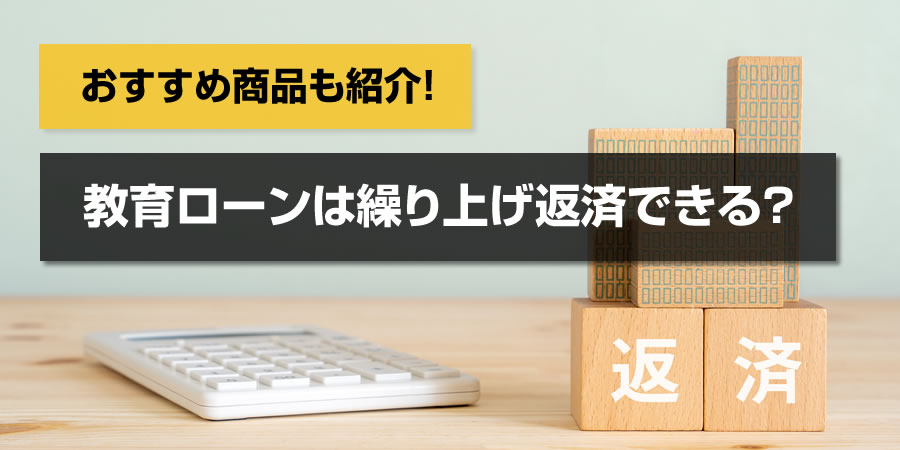【第56回】【母子家庭向け】利用しやすい教育ローンとは?国の教育ローン・母子父子寡婦福祉資金を解説

本記事では、代表的な「国の教育ローン」そして「母子父子寡婦福祉資金」について解説します。また、もしこれらの支援制度が利用できなかった場合の対応方法もあわせて説明するので、ぜひ参考にしてください。
この記事は約12分30秒で読むことができます。
お急ぎの方、教育ローンのランキングを知りたい方は、このページ下部のこちらをご覧ください。
1. 母子家庭向けの主な教育ローンは2つ

国の教育ローンとは正式名称を「教育一般貸付」といい、日本政策金融公庫が主体となっています。
また、母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、厚生労働省が行う貸付事業です。居住する都道府県の福祉窓口に申請することで、必要な資金の貸付が受けられます。
2. 国の教育ローン(日本政策金融公庫の教育一般貸付)とは
日本政策金融公庫が行っている教育一般貸付、「国の教育ローン」の概要は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入金額 | 最高350万円 |
| 金利 | 1.65%(固定金利) |
| 返済期間 | 最長15年 |
※参考:教育一般貸付(国の教育ローン)|日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
2-1. 特徴
国の教育ローンは、日本学生支援機構の奨学金と併用できる点や、対象校の多さや幅広い用途に対応している点が特徴です。比較的低い金利(固定金利)で借りることができ、子どもの数によって所得制限が設けられています。
ただし優遇措置があり、母子家庭はその対象となるため、金利や返済期間などが優遇されます。 () 表
| 金利 | 1.25%(固定金利) |
|---|---|
| 返済期間 | 最長18年 |
| 保証料 | 通常の3分の2(ただし、連帯保証人を立てる場合は保証料不要) |
そのほか低所得世帯(年収200万円以下)にも優遇措置が設けられています。
| 金利 | 1.25%(固定金利) |
|---|---|
| 返済期間 | 最長18年 |
| 保証料 | 通常(ただし、連帯保証人を立てる場合は保証料不要) |
2-2. 借入条件
原則として世帯年収790万円以下の人が利用できますが、子どもの数によって世帯年収(所得)の上限が異なります。また、他の金融機関の教育ローンのような所得制限の下限は設けられていません。
そして、ここでいう子どもの数とは、申込み者の世帯で扶養している子どもの数のことを指し、年齢要件や就学要件はありません。
上限額については給与所得者は年収を、それ以外の事業所得者は所得の額を参考にしてください。
| 子どもの数 | 世帯年収(所得)の上限額 |
|---|---|
| 1人 | 790万円(600万円) |
| 2人 | 890万円(690万円) |
| 3人 | 990万円(790万円) |
| 4人 | 1,090万円(890万円) |
| 5人 | 1,190万円(990万円) |
このように、扶養している子どもの数が増えるほど、年収(所得)の上限額が上がる仕組みになっています。
2-2-1. 条件付きで緩和してもらえるケースもある
日本政策金融公庫の教育ローンは、所定の条件を満たすと条件付きで所得制限を緩和されることがあります。例えば、前年の世帯収入要件では条件を満たせないものの、今年の収入が大幅に下がる見込みがあるなどの場合です。
自分で条件に該当していることを確認できた場合はもちろん、条件を満たしているか判断できない場合は、まずは日本政策金融公庫へ相談してみましょう。
2-2-2. 扶養している子どもが2人だと所得制限緩和の可能性あり
扶養している子どもの数が2人までの場合、要件を満たすことで、収入(所得)上限額が990万円(790万円)まで緩和されます。その要件とは以下のいずれかに当てはまる場合です。
- 勤続もしくは営業年数3年未満
- 居住年数1年未満
- 世帯の誰かが自宅外通学者(予定も含む)
- 申込み者またはその配偶者が単身赴任
- 資金使途が海外留学資金
- 申込み者の年収(所得)に占める借入返済額の負担率が30%超
- 親族に要介護(要支援)認定を受けている人がおり、その介護費用を負担している
- 大規模災害によって罹災した
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世帯収入(所得)が減少した
上記の特定条件を満たすと、世帯年収の上限が最大990万円に緩和されます。通常は子ども1人あたり790万円、2人だと890万円の所得制限が設定されているため、990万円に緩和されるのは大きな変化です。
2-3. 対象となる学校
国の教育ローンの対象となる学校は、中学校卒業の人を対象とした以下の学校です。
| 大学・専門学校 | 大学、大学院(法科大学院など専門職大学院を含む)、短期大学、専修学校、各種学校(予備校、デザイン学校など) |
|---|---|
| 高等学校 | 高等学校、高等専門学校、 |
| 特別学校 | 特別支援学校、語学学校、外国の高等学校など |
| その他 | その他職業能力開発校などの教育施設 |
原則として、履修期間が6カ月以上あることが要件です(外国の学校については3カ月以上)。そして、以下に該当する場合は対象外となる点に注意してください。
- 正規の学籍で在籍しない場合(研究生や聴講生など)
- 学生が公務員として通う学校(気象大学校、税務大学校など)
- 企業内教育訓練施設
また、大学などであっても対象外となる学校もあります。不明な場合は教育ローンコールセンターに問い合わせて、確認するようにしましょう。
2-4. 手続きに必要なもの
申込み手続きの際には、以下の書類が必要となります。
- 借入申込書
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の原本(世帯全員が記載されたもの)
- 運転免許証もしくはパスポート
- 源泉徴収票もしくは確定申告書の控え(直近のもの)
- 預金通帳や領収書など、支払い状況(住宅ローンもしくは家賃、公共料金など)が分かるもの
また、申込みの内容が「入学資金」もしくは「在学資金」の場合で、必要となる書類が異なる点にも注意が必要です。
- 入学資金の場合:合格通知書など合格を確認できる書類
- 在学資金の場合:学生証のほか、授業料納付通知書など
さらに、自宅外通学の場合はそれを確認できる書類(不動産賃貸契約書、住民票など)が必要になります。
申込み手続きはインターネットで行えるほか、日本政策金融公庫だけでなく、銀行、信用金庫などでも可能です。
2-5. 利用時の注意
国の教育ローンを利用するには、あくまでも安定した収入があることが要件です。なぜなら、ローンである以上、必要があるからです。そのため、申込み者の返済能力も審査されます。
生活保護者における生活扶助は収入とみなされないため、生活保護を受けている人は申込み対象外となる可能性がある点に注意が必要です。
3. 母子父子寡婦福祉資金とは

母子父子寡婦福祉資金とは、20歳未満の児童を扶養しているひとり親もしくは寡婦に貸し付けられる資金で、その用途によって条件が異なります。教育のためであれば「修学資金」となり、大学に進学する場合の貸付内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 貸付上限金額 | 月額14万6,000円 |
| 金利 | 0%(無利子) |
| 返済期間 | 20年以内 |
3-1. 特徴
上でも述べたとおり、対象者は20歳未満の児童を養育するひとり親です。そのため、母子家庭や父子家庭、そして寡婦が当てはまります。民間の教育ローンよりも審査が柔軟な傾向にある点が特徴となっており、利用目的によって貸付額の上限が決まっています。
そして、教育にかかわる「修学・就学支度資金」は、親が借りる場合は子どもを連帯債務者、子どもが借りる場合は親を連帯債務者にする必要がある点に注意が必要です。
3-1-1. 利用目的に応じた限度額一覧
母子父子寡婦福祉資金の資金項目および利用目的は多岐に渡っており、それぞれに以下のとおり貸付上限金額が設定されています。
| 資金項目 | 利用目的 | 貸付上限金額 |
|---|---|---|
| 修学資金 |
高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金
|
・高校、専修学校(高等課程):5万2,500円
・高等専門学校: [1~3年]5万2,500円 [4~5年]11万5,000円 ・専修学校(専門課程): 12万6,500円 ・短期大学: 13万1,000円 ・大学: 14万6,000円 ・大学院(修士課程): 13万2,000円 ・大学院(博士課程): 18万3,000円 ・専修学校(一般課程): 5万1,000円 (私立を想定。額はいずれも月額) |
| 技能習得資金 |
自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
|
月額 6万8,000円
一括 81万6,000円 運転免許 46万円 |
| 修業資金 |
事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金
|
月額 6万8,000円
|
| 就職支度資金 |
就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金
|
10万円
|
| 医療介護資金 |
医療又は介護を受けるために必要な資金
|
医療:34万円
介護:50万円 |
| 生活資金 |
知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)者の生活を安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金
|
月額 10万5,000円
|
| 住宅資金 |
住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
|
150万円
|
| 転宅資金 |
住宅を移転するため住宅の貸借に際し必要な資金
|
26万円
|
| 就学支度資金 |
就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 |
小学校:6万4,300円
中学校:8万1,000円 国公立高校等:16万円 修業施設:28万2,000円 私立高校等:42万円 国公立大学・短大・大学院等:42万円 私立大学・短大等:59万円 (高校以上は自宅外通学の場合の限度額) |
| 結婚資金 |
母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童及び寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金
|
30万円
|
※引用:母子父子寡婦福祉資金貸付制度|内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html
3-2. 借入条件
借入条件としては、まず「20歳未満の児童を扶養するひとり親であること」があげられます。そして、本人の合計所得金額が500万円以下でなければなりません。
また、母子家庭の場合、子どもが扶養から外れても寡婦という立場で利用することができます。寡婦とは婚姻歴がある女性で、配偶者と死別もしくは離別している人を指します。ひとり親と寡婦の違いは以下のとおりです。
| ひとり親 | 寡婦 | |
|---|---|---|
| 婚姻歴 | 問わない | 婚姻歴あり |
| 性別 | 問わない | 女性である |
| 扶養している子ども | 要 | 不要(いなくてもよい) |
| 配偶者 | いない | |
| 事実婚 | なし | |
資金項目によって条件が異なるため、利用の際には 公式サイト* で必ず確認するようにしましょう。
* https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/23.html
3-3. 手続きに必要なもの
手続きは住んでいる自治体の福祉窓口で行います。その際には以下の書類を準備するようにしましょう。
- 貸付申請書
- 戸籍謄本(発行日から1カ月以内のもの)
- 世帯全員の住民票(発行日から1カ月以内のもの)
- 印鑑登録証明書(発行日から1カ月以内のもの)
- 所得を証明する書類(連帯保証人の収入を証明するために必要)
- 本人確認書類
自治体によって必要な書類が異なるケースがあります。役所での手続きの際は必ず事前に必要書類を確認し、もれのないように準備しておきましょう。
3-4. 利用時の注意
母子父子寡婦福祉資金は、他の公的支援制度と併用できません。つまり、学生支援機構が提供している奨学金や生活福祉資金貸付制度、生活保護との併用はできない点に注意してください。
4. 国の教育ローン・母子父子寡婦福祉資金を利用できない場合の対処法とは

では、国の教育ローンおよび母子父子寡婦福祉資金を利用できない場合はどうしたらいいのでしょうか。
4-1. 他の制度をうまく活用する
国の教育ローンや母子父子寡婦福祉資金以外にも、国の支援制度があります。
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 児童扶養手当 | ・ひとり親世帯等など、父親もしくは母親と生計を同じくしていない児童に対して支給される手当。 ・所得制限がある ・全部支給の場合、月額4万3,160円が支給される(令和3年度額)。 |
| 自立支援教育訓練給付金 | ・母子家庭の母、父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもの。 ・対象の教育訓練を受講し、終了した場合にその経費の60%が支給される。 |
| ひとり親世帯臨時特別給付金 | ・児童扶養手当を受給しているひとり親世帯が対象。 ・給付額は1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円。 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて児童扶養手当受給レベルの水準になった世帯も給付対象となる。 |
これらの制度を上手に活用し、教育費用に充てるようにしましょう。
4-2. 民間の教育ローンの利用を検討する
銀行の教育ローンや消費者金融のカードローンなど、民間企業からの借り入れも視野に入れてみましょう。利用条件は金融機関やローン商品によって異なりますが、ひとり親でも収入が安定しており、条件を満たしていれば利用できます。
民間の教育ローンには、「審査から融資までの期間が短い」点や、「比較的まとまった資金を借り入れできる」こと、さらには「資金使途の範囲が広めに設定されている」ことからも、利用しやすいというメリットがあります。
ただし、国の教育ローンなどに比べると金利が高めに設定されている点に注意が必要です。安易に申込むのではなく、借りた後にきちんと返済できるか返済計画をきちんと立ててから申込むようにしてください。
母子家庭は国などの教育ローンを利用しやすい!もし難しい場合は民間への申込みを検討する 
母子家庭を含むひとり親世帯は、国の教育ローンや母子父子寡婦福祉資金を利用しやすい環境にあります。借入条件も比較的良く、さらに優遇措置も設けられていることから、この機会に一度利用を検討してみてはいかがでしょうか。
また、国の教育ローンや母子父子寡婦福祉資金を利用できなかったとしても、条件を満たせば民間の教育ローンを利用できる可能性があります。利用できなかったからと諦めるのではなく、利用できる民間の教育ローンがないかどうかを探すことも大切です。
- 金利ランキング
ライター紹介
- 氏名:
- 新井智美
- 保有資格:
- ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
- 主なキャリア:
- コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)を行う他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に金融メディアへの執筆及び監修も行い、現在年間200本以上の執筆及び監修をこなしている。これまでの執筆及び監修実績 は1,500本以上。
教育ローンに関するよくある質問
ここからは教育ローンについてよくある質問について、その回答と合わせて紹介します。
- 教育ローンにはどんな種類がある?
- 民間の金融機関が提供する「民間の教育ローン」と、日本政策金融公庫が提供する「国の教育ローン」の2種類あります。国の教育ローンは民間の教育ローンより金利は低く設定されている一方で利用条件を満たさないと利用ができません。民間の教育ローンは借入可能額の上限が高い金融機関もあるため、用途に合わせて申込みを検討しましょう。
- 教育ローンの金利相場はどのくらい?
- 教育ローンの金利相場は約1%~4%になります。国の教育ローンは固定金利で1.95%です(令和5年5月時点)。民間の教育ローンの金利はさまざまで、固定金利か変動金利によっても異なります。キャンペーンの適用により低金利で借りられる場合もあるので、申込みの際は事前に各金融機関のローン情報を確認しましょう。
- 教育ローンの審査基準とは?
- 教育ローンの審査基準は、契約者に返済能力があるかを重視されるのが一般的です。金融機関によって審査基準は異なりますが、他に返済をしないといけない負債があったり信用情報にキズがあると審査に通りにくい可能性があります。
- 教育ローンの返済方法は?
- 教育ローンの返済方法は、一般的に「元利均等返済」になります。元利均等返済は、毎月の返済額が均等になるように設定されるので返済計画が立てやすいのがメリットです。返済が進むほど元金が減るので利息額は減りその分元金の返済額が増えていきます。一括返済や繰上返済を利用して利息を抑えることも検討しましょう。
- 教育ローンのお金を借りるまでの流れは?
- 教育ローンを利用するには、まずローンの申込みをしてから各金融機関で実施する仮審査と本審査に通過する必要があります。本審査を受けるには契約者の本人確認書類などの書類提出が必要となります。審査に通過をして契約を締結後に契約者の口座に入金がされる流れとなります。
- 教育ローンを利用するには保証人が必要?
- 教育ローンは一般的に保証人が不要です。理由は保証会社が保証人の役割を担っているためです。保証会社とはローンの契約者が返済できなくなった際、本人に代わり借入先の金融機関に返済を行う会社です。また、国の教育ローンも教育資金融資保証基金の保証を受ける場合は保証人は不要になりますが、保証人を立てることも可能です。
- 教育ローンの借り入れまでの日数はどのくらい?
- 教育ローンの申込みから借り入までの日数は金融機関によって異なります。民間の教育ローンの場合は一般的に2週間~3週間程度です。国の教育ローンは3週間から1ヵ月と民間の教育ローンよりも時間がかかるため余裕を持って申込みをするとよいでしょう。
ライター紹介

- 氏名
- 新井 智美(あらい ともみ)
- 保有資格
- ファイナンシャルプランナー(CFP®)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
- 主なキャリア
- コンサルタントとして個人向け相談(資産運用・保険診断・税金相談・相続対策・家計診断・ローン・住宅購入のアドバイス)を行う他、資産運用など上記相談内容にまつわるセミナー講師(企業向け・サークル、団体向け)を行うと同時に金融メディアへの執筆及び監修も行い、現在年間200本以上の執筆及び監修をこなしている。これまでの執筆及び監修実績 は1,500本以上。
関連記事
人気記事
当サイトについて
ローンプラス(以下、当サイト)は株式会社オプトにより運営・管理されています。
当サイトは各種ローン商品などに関する情報の提供を目的としており、ローンの申込み、及び契約締結の代理、媒介、斡旋などを行うものではありません。
掲載情報について
当サイトに掲載されている融資の審査に関する内容につきましては、特定の金融機関がお申込みされたお客様に対して独自に行うものであり、当社は審査の過程および結果については一切関与しておりません。また、特定の金融機関の審査への適合性、正確性、完全性について保証するものではありません。融資の審査に関する情報などに基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。ローンの申込み、及び契約締結に関するすべての決定は、ご自身の判断で行うようお願いいたします。
融資の審査に関する情報や、金利、借入条件、キャンペーンなどの詳細については、金融機関から直接提供される正確かつ最新の情報を必ずご確認ください。
なお、当サイトに掲載されている情報は無断転載、無断使用を固く禁じます。