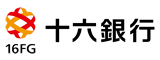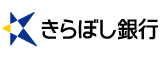【第31回】住宅ローン「フラット35」の特徴は?利用条件や民間ローンとの違いを解説

この記事は約7分30秒で読むことができます。
お急ぎの方、住宅ローンのランキングを知りたい方は、このページ下部のこちらをご覧ください。
1.長期固定金利型住宅ローン「フラット35」とは?
「フラット35」の概要やメリット・デメリットを解説します。この記事で扱う金利などの情報は、2021年5月14日時点のものです。
1-1.「フラット35」の特徴
「フラット35」は、国土交通省と財務省が管轄する住宅金融支援機構が、民間の金融機関と連携して提供する住宅ローンです。利用者が契約した民間の住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取る制度で、良質な住宅の安定的な普及を目的として運用されています。「フラット35」の一番の特徴は、最長35年の全借入期間に固定金利が適用される住宅ローンだという点にあります。たとえば、借入時の金利が1.3%だった場合は完済まで金利1.3%が適用され、市場金利の影響を受けません。さまざまなタイプのサービスやオプションが用意されている点も「フラット35」の特徴です。以下で主なラインナップを紹介します。
商品ラインナップ
- 「フラット35」:返済期間15年以上35年以下
- 「フラット20」:返済期間15年以上20年以下で優遇金利が適用される
- 「フラット35」リノベ:中古住宅とリフォームのセット利用で優遇金利が適用される
ほかにも、国民の住生活支援やまちづくり推進に役立つ「フラット35」地域連携型や家賃返済特約付き「フラット35」などのサービスがあります。「フラット35」を利用するときは、住宅金融支援機構と連携している民間の金融機関に直接申込みましょう。住宅金融支援機構の公式サイトには「フラット35」を取り扱っている金融機関の一覧が掲載されています。ただし、適用される金利や手数料は金融機関ごとに異なる点に注意が必要です。同じ「フラット35」でも、選んだ金融機関によって返済総額や費用負担が変わってきます。
1-2.「フラット35」のメリット・デメリット
「フラット35」にはメリットもありますが、デメリットも存在します。自分に向いているかどうかを見極めるためにも、ポイントを押さえておきましょう。
メリット
「フラット35」は固定金利型の住宅ローンです。返済期間を通して一定の金利が適用されるため、返済計画や家計管理が安定しやすい点が魅力です。保証会社の利用にかかる保証料や繰上返済手数料は無料で、連帯保証人も必要ありません。ただし、融資事務手数料は発生します。最低年収などの所得に関する制限がない点もメリットです。民間の住宅ローンで不利になりやすい個人事業主や年金生活者でも、条件を満たせば利用できます。
デメリット
固定金利は、デメリットにもなりえます。将来的に市場金利が下がっても恩恵を受けられないためです。ほかの金利タイプを選ぶほうが、返済総額が抑えられる場合があります。金利タイプについては後段で詳しく紹介します。借入時の金利が高めに設定されている点にも注意が必要です。「フラット35」は、多少金利が高くても安定性を重視したい人に向いています。
1-3.「フラット35S」との違い
「フラット35S」は、「フラット35」のオプションサービスです。名前が似ているため、混同しやすい点に注意しましょう。「フラット35S」とは、耐震性や省エネルギー性などの条件を満たす良質な住宅を購入する際に、「フラット35」の金利を一定期間引き下げる制度です。
「フラット35S」には、金利Aプランと金利Bプランがあります。
- 金利Aプラン:借入当初から10年間、金利を年0.25%引き下げ
- 金利Bプラン:借入当初から5年間、金利を年0.25%引き下げ
「フラット35S」が適用されれば金利が下がり、返済総額も減ります。新築はもちろん中古住宅でも利用できるため、購入予定の住宅が条件を満たすかどうかチェックしておきましょう。
2.「フラット35」の主な利用条件
「フラット35」は民間の住宅ローンとは違って、利用条件が明確に提示されています。審査対策が立てやすい点はメリットですが、条件を満たさない場合は年収が高くても審査に落ちる点に留意しましょう。ここからは、「フラット35」の主な利用条件を解説します。
2-1.その1.年齢・借入金額・借入期間
「フラット35」の主な申込要件は以下のとおりです。- 年齢:申込時の年齢が満70歳未満(親子リレー返済を除く)
- 外国籍の人は「永住者」または「特別永住者」の資格が必要
- 借入金額:100万円以上8,000万円以下
- 最短借入期間:申込者または連帯債務者が60歳未満の場合は15年以上、満60歳以上は10年以上
- 最長借入期間:「80歳から申込時の年齢を引いた期間」と「35年」のうち、いずれか短いほう
たとえば、40歳で申込む場合は80歳-40歳=40歳となるため、35年の最長借入期間が適用されます。親子リレー返済では、後継者の年齢が基準となります。「フラット35」は、建設費または購入価格の90%までの借り入れが基本です。90%を超える借り入れを希望すると、金利が高くなり審査のハードルも上がります。
2-2.その2.総返済負担率
「フラット35」の利用条件のひとつに、総返済負担率があります。総返済負担率とは、「すべての借り入れ」の年間合計返済額が年収に占める割合です。
総返済負担率=「すべての借り入れ」の年間合計返済額÷年収
「すべての借り入れ」には、「フラット35」やカードローン、教育ローンなどが含まれます。賃貸予定または賃貸中の住宅にかかる借入金も合算対象となるため、利用している人は注意してください。
「フラット35」が定める総返済負担率は以下のとおりです。
- 年収400万円未満:総返済負担率30%以下
- 年収400万円以上:総返済負担率35%以下
たとえば、年収400万円で年間合計返済額が150万円だった場合の総返済負担率は、150万円÷400万円=37.5%となり、「フラット35」を利用できません。年収600万円でほかに借り入れがない場合なら、年間210万円(月額約17万円)まで「フラット35」を利用できます。住宅ローン以外の借り入れが多いと「フラット35」で借りられる金額が減ってしまいます。
2-3.その3.住宅の技術基準
「フラット35」は質の良い住生活の支援を目的としているため、住宅金融支援機構が定めた基準を満たす住宅を購入する場合にのみ利用可能です。専門の適応証明検査機関が立地や耐久性、維持管理状況などを検査し、基準を満たす場合は「適合証明書」が発行されます。
新築と中古の物件に共通する技術基準は以下のとおりです。
- 接道:原則として一般の道に2メートル以上接する
- 住宅の規模:一戸建て住宅は70平方メートル以上、マンションは30平方メートル以上
- 住居の規格:原則として2つ以上の居住室ならびに炊事室、トイレ、浴室の設置
- 住宅の構造:耐火構造、準耐火構造または耐久性基準に適合
新築か中古か、一戸建て住宅かマンションかによって基準が細かく定められているため、物件選びの際にチェックしておくことをおすすめします。
3.「フラット35」と民間金融機関住宅ローンの違いを比較
「フラット35」は、民間の金融機関が住宅金融支援機構と連携して提供する住宅ローンです。一方、民間の金融機関が独自に住宅ローンを提供している場合があります。たとえば、日本最大手の住宅ローン専門金融機関・ARUHIは「フラット35」も扱っていますが、独自の住宅ローン「ARUHI スーパーフラット」も提供しています。「フラット35」と一般的な住宅ローンの違いがわからないと混乱しやすいため、しっかり区別して特徴を把握しておきましょう。
3-1.金利の種類
「フラット35」は全期間固定金利型ですが、民間の住宅ローンには変動金利や固定金利期間選択型などの金利タイプがあります。変動金利とは、市場金利の変化に伴って商品の金利も変動する金利タイプです。市場金利が下がると金利も下がるため、利息負担が軽くなります。ただし、市場金利が上がるリスクも抱えています。
固定金利期間選択型とは、一定期間は固定金利が適用され、期間を過ぎた時点であらためて金利タイプを選べる仕組みです。たとえば、固定期間3年型を選ぶと最初の3年間は固定金利が適用され、4年目に再度固定金利を選ぶか変動金利に切り替えるかを決められます。
民間にも長期固定金利型の住宅ローンを低金利で提供している金融機関は存在しますが、高い保証料や繰上返済手数料がかかる商品もあります。住宅ローンは金利のみではなく、必ずコストの合計額で判断しましょう。
3-2.審査の基準
民間の金融機関は、通常住宅ローンの審査内容を公開していません。正確な基準がわからないため、対策しづらい点がネックです。一方、「フラット35」は公式サイトなどに利用条件を明記しており、正しく対応すれば審査に通る可能性が高まります。「フラット35」を扱う住宅金融支援機構は営利を目的としていないため、一般的な住宅ローンに比べると審査に比較的通りやすいといわれています。ただし、民間の住宅ローンと同様に個人信用情報がチェックされる点には注意が必要です。携帯電話料金やカードローンなどの支払いに滞納があると審査のハードルが上がります。
3-3.団体信用生命保険への加入義務
団体信用生命保険(以下団信)とは、ローンを組んだ人が死亡・高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンを完済する仕組みです。ローンが残っていても返済の必要がなくなるため、残された家族はマイホームを失わずに済みます。民間の住宅ローンでは団信への加入を義務付けているケースが一般的で、健康上の理由などで団信に加入できない人は利用できません。「フラット35」も原則として団信への加入が求められますが、未加入でも契約は可能です。
「フラット35」の団信は、2017年10月から保険料が返済額に上乗せされる制度に改正されました。団信に加入しない場合は、保険料の分だけ金利が下がります。とはいえ、万が一の事態に自己資金で対応できない可能性がある人には、団信への加入がおすすめです。
以下で、楽天銀行の「フラット35」と楽天銀行住宅ローンを紹介します。「フラット35」と民間の住宅ローンの違いを把握するために役立ててください。
楽天銀行の「フラット35」
※建設費・購入価額が借入額に占める割合が90%以内、団信加入、新規借入の場合- 金利:返済期間15年以上20年以下で年1.24%、21年以上35年以下で年1.37%
- 融資事務手数料:借入金額の1.10%
楽天銀行の住宅ローン(新規借入)
- 申込条件:借入時の年齢が65歳6カ月未満で完済時の年齢が満80歳未満、前年の年収が400万円以上、総返済負担率が30%~35%以下、など
- 金利:固定金利選択型(10年)で年1.030%~1.680%、変動金利で年0.537%~1.187%(実際の金利は借入条件や審査結果で決まる)
- 保証人・保証料・繰上返済手数料なし、団信加入必須
- 融資事務手数料:一律33万円(税込)
※2021年5月14日時点の情報を記載しています。
利用条件に注意して「フラット35」の審査通過を目指そう!
「フラット35」は、固定金利で返済計画が立てやすく、利用条件が明確で審査対策もしやすい住宅ローンです。同じ「フラット35」でも金融機関ごとに金利や手数料などの詳細が異なるため、比較検討しながら自分にあったサービスを選んでください。民間の住宅ローンとの違いも正しく理解して、最適な金融機関に申込みましょう。
- 金利ランキング
ライター紹介
- 氏名:
- ひまり
- 主なキャリア:
- Webライター歴4年。元SE、専攻は心理学。ITおよびカードローンやキャッシング、税金関係の記事が得意分野。複数メディアのライターとして寄稿している。
- 保有資格:
- 基本情報技術者試験
住宅ローンに関するよくある質問
ここからは住宅ローンについてよくある質問について、その回答と合わせて紹介します。
- 変動金利と固定金利どちらがよい?
- 変動金利は固定金利より金利が低い傾向にありますが、金利動向に連動して変動するため、貯蓄に余裕があったり、今後収入が増える見込みがある人に向いていると言えます。一方、固定金利は一定期間同じ金利のため完済までのスケジュールを立てやすい点がメリットになり、無理なく返済したい人に向いていると言えます。
- 住宅ローンの審査基準とは?
- 住宅ローンの審査基準は返済能力をチェックするために「借入時・完済時の年齢」「健康状態」「勤務先・勤続年数」「年収」「担保評価」などになります。 物件の担保価値は契約者が返済できなくなった場合を考慮して評価されるため、借入前に不動産の価値を調べておくとよいでしょう。
- 住宅ローンの返済方法は?
- 住宅ローンの返済方法には「元利均等返済」と「元金均等返済」の2種類があります。元利均等返済とは返済額が毎月一定のため、返済プランを立てやすいことが特徴です。元金均等返済は返済が進むと返済額が減っていくため、元利均等返済と同期間での返済では返済総額が少なくなります。
- 住宅ローンでお金を借りるまでの流れは?
- 住宅ローンを借り入れるまでの流れは、ローンの申込みをしたあと仮審査、住宅の売買契約、本審査を経て契約、融資実行(住宅の引き渡し)となります。本審査では本人確認資料や物件確認資料、収入に関する書類などが必要となり、本人属性や他社借入状況など総合的に判断した上で借入可能額の上限が決定します。
- 住宅ローンを利用するには保証人が必要?
- 住宅ローンは基本的に保証人なしでお金を借りることができます。理由としては購入する自宅が担保となるため、契約者が返済ができなくなった時は住宅を売却することで資金を回収できることや、保証会社に一定の保証料を支払うため、保証会社が保証人の代わりの役割を担うことができるためです。
- 住宅ローンの借り入れまでの日数はどのくらい?
- 住宅ローンの借り入れまでの日数としては事前審査が1週間程度、本審査が2週間~3週間程度かかるため、およそ1ヵ月ほどかかります。必要書類に不備があったり、借入希望金額が大きい場合には審査が長期化し、更に時間を要します。
ライター紹介
- 氏名
- ひまり(ひまり)
- 主なキャリア
- Webライター歴4年。 もともとシステムエンジニアだったが、結婚、出産、育児と専業主婦の期間を活かして知識を習得し始めたことがきっかけで、現在はカードローンやキャッシング、税金関係の記事を得意とし、複数メディアのライターとして寄稿している。現在は簿記の勉強中。
関連記事
人気記事
当サイトについて
ローンプラス(以下、当サイト)は株式会社オプトにより運営・管理されています。
当サイトは各種ローン商品などに関する情報の提供を目的としており、ローンの申込み、及び契約締結の代理、媒介、斡旋などを行うものではありません。
掲載情報について
当サイトに掲載されている融資の審査に関する内容につきましては、特定の金融機関がお申込みされたお客様に対して独自に行うものであり、当社は審査の過程および結果については一切関与しておりません。また、特定の金融機関の審査への適合性、正確性、完全性について保証するものではありません。融資の審査に関する情報などに基づいて被ったいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。ローンの申込み、及び契約締結に関するすべての決定は、ご自身の判断で行うようお願いいたします。
融資の審査に関する情報や、金利、借入条件、キャンペーンなどの詳細については、金融機関から直接提供される正確かつ最新の情報を必ずご確認ください。
なお、当サイトに掲載されている情報は無断転載、無断使用を固く禁じます。